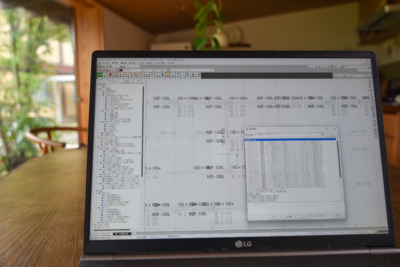空間を考える際に大切にしていることの一つに、「メリハリをつけること」があります。空間にメリハリをつけるとは、具体的にどういうことかを設計者としてのスタンスから説明してみます。
小さな空間やワンルーム空間では、空間が均一になり、変化に乏しい単調な印象になりがちです。(その空間に単調さが意図的に求められる場合を除きます。)しかし、空間にメリハリをつけることで、変化や複雑さが生まれ、多様な質を持った空間へと変化させることができます。
人間はその時々で気分が一定ではありません。一人で狭い空間に籠っていたい時もあれば、明るく活動的な気分の時もあります。その時々の気分に応じて居場所が選べる、そんな多様な質(広さ、高さ、明るさなど)を持った柔軟な建築空間であれば、日々を心地よく過ごせるのではないかと考えています。
空間の広さに変化をつける

人は狭い場所から広い開けた場所に出た時に、その変化の差を感じます。当然のことながら、広い場所からそれよりもちょっと広い場所へ移動したとしても、大きな空間の変化がないので、差を感じることはありません。よって、その差を大きくすることが肝心です。
狭い所はぎゅっと狭く、広くする所はがらんと広く、大きく変化をつける。そのように空間を構成すれば、変化に富んだ空間を実現することができます。一気に変化させれば劇的に、次第に変化させていけば段階的にと、その変化の速度を変えることで、変化の度合いを変えることもできます。

こちらの写真は、1.5帖の小さな書斎スペースです。カウンターを設け、正面に外を望める窓を設けています。やや暗めの仕上げ材を選んで、洞穴の中にいるような雰囲気にしました。ここに一人で籠っていると、時間が経つのを忘れてしまいます。
設計を進めていく段階で、ついつい部屋を広くしてしまいがちですが、あえて狭くするのも一興です。写真に上げたような一人で籠れるようなユニークな空間が生まれるかもしれません。趣向を変えて、できる限り狭くと、設計者にリクエストしてみてはいかがでしょうか。
天井高さに変化をつける

天井の低い空間から天井の高い空間へ移動すると、上へと広がる高揚感を感じます。一般的には天井高さを一定に揃えることが多いのですが、それですと変化がなく、どの部屋に移動したとしても均一にしか感じません。
上の写真は、屋根勾配なりに天井を張ったLDKです。LDKは一番高い場所で天井高3.2mと高めに設定していますが、正面奥に見えている廊下やパントリーは天井高2.2mと低めに設定し、廊下からLDKに入った際に、上昇感を感じるような構成を創り出しています。

天井高の低い通路から、天井の高いLDK方向を見た写真です。大きく空間の質が変わっているのが読み取れます。
書斎や寝室などの落ち着いた雰囲気にしたい部屋は、思い切って天井高を下げてみるのも一興です。逆にLDKには天井高さを高めに。大事なことは、変化の落差を大きくすることです。
明暗差を創り出す

窓の大きさや方位などを変え、部屋に差し込む光量に変化を与え、部屋ごとに明・暗の変化をつけます。明るくしたい部屋は、南側に大きく窓を設けて明るく、明るさを抑えたい部屋は、窓を絞って暗めに。
部屋のボリュームに対しての窓の割合や、窓を取り付ける高さ、方位などにより、室内にどれくらいの光が差し込んでくるかをイメージして空間構成を考えます。

窓から入るの陽の光だけでなく、照明による照度差を意識することも大切です。照明使用時には各部屋の照明の明るさを変えることで、空間に奥行きを与えることができます。明暗差を大きく、やや暗めにすれば、落ち着いた雰囲気を与えることができます。
カウンター上だけを照明で照らして印象的な雰囲気を創り出したり、全般的に明るくして活動的な雰囲気を創り出すなど、さまざまな演出が可能です。
明/暗の変化と合わせて、広い/狭い、高い/低いなどの変化を各空間に与えるのが効果的です。相乗効果が起き、より変化に富んだ空間を実現できます。
強弱の変化をつけること

空間にメリハリをつけることは、単調で均一な空間を避け、居住者のその時々の気分に応じて居場所が選べる「多様な質を持った包容力のある建築」を実現するために、私が大切にしている設計スタンスです。
このメリハリを生み出すための最も重要な原則は、「強弱の変化をつける」ことです。具体的には、単に広さ、天井高さ、明暗の差を設けるだけでなく、変化の差や落差を大きくすることが肝心です。
これらの要素(広い/狭い、高い/低い、明/暗)を組み合わせ、強弱の度合いをチューニングすることで相乗効果が生まれ、変化に富んだ、日々を心地よく過ごせる空間が実現します。