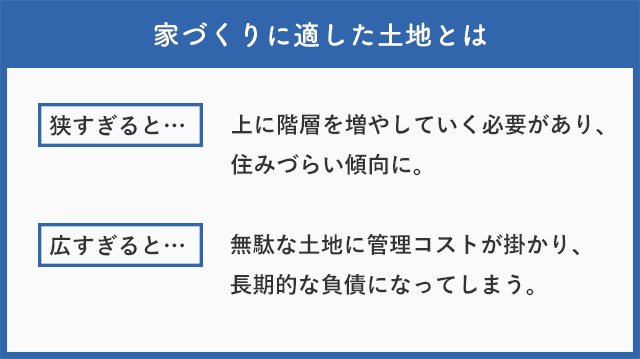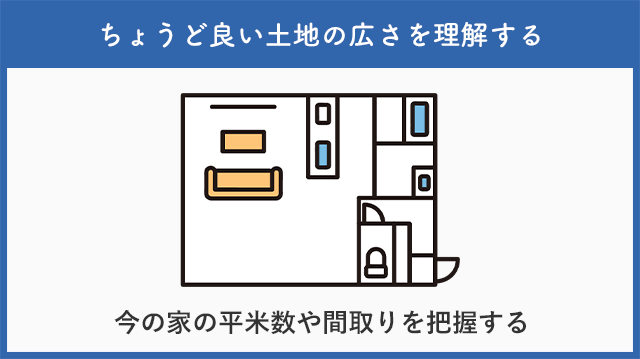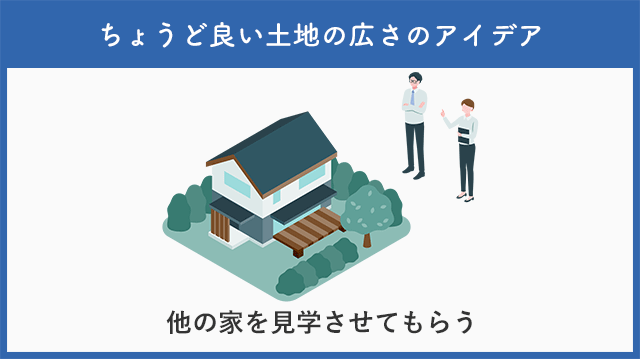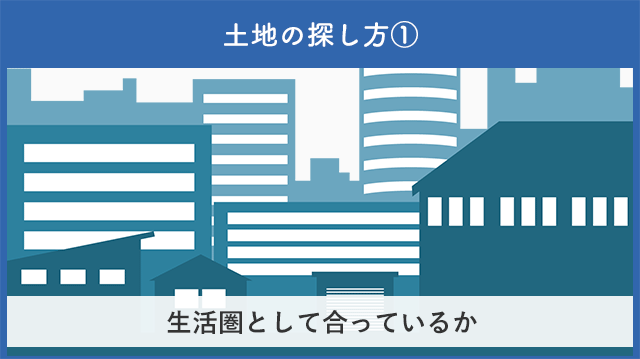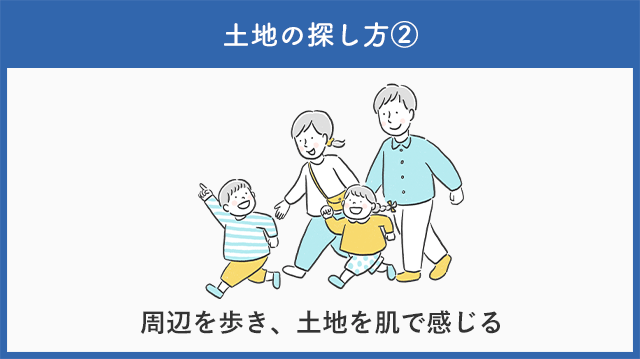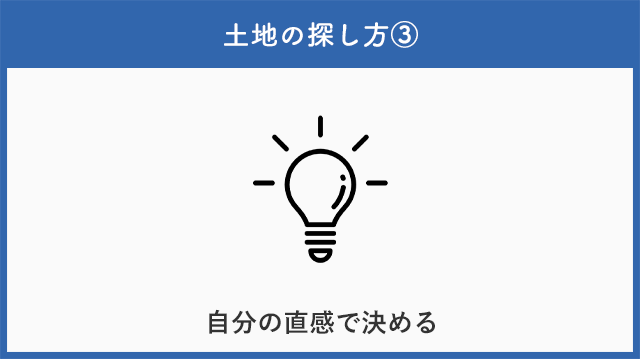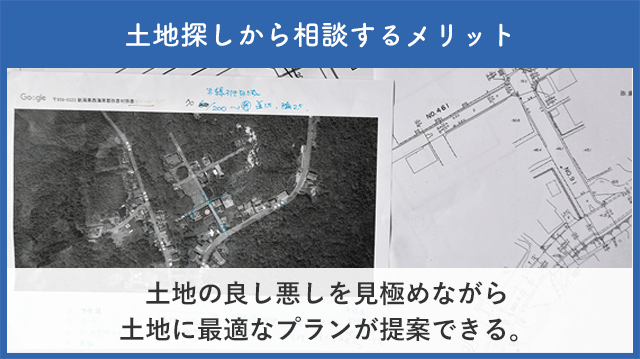【第4回】家や土地の広さは何を手がかりに決めれば良いですか?
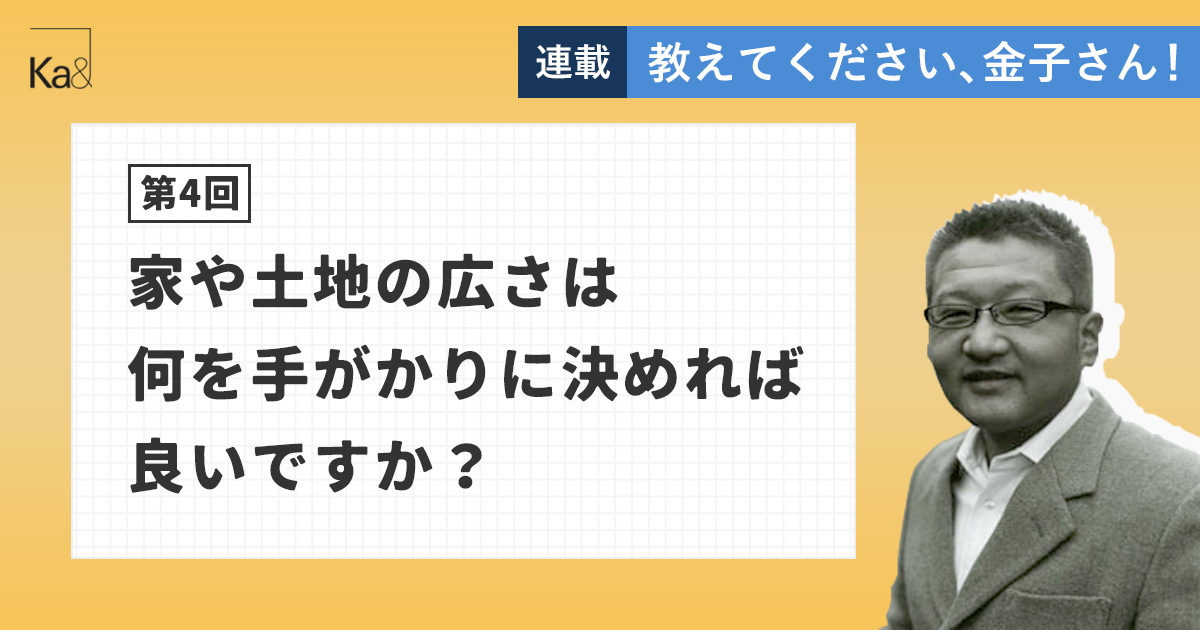
家づくりの費用構造について理解を深め、少しずつ家の設計に興味が湧いてきた松永さんご夫妻。自分たちにとっての理想の家の大きさには、実は土地が関係していたのです。今回は家や土地の広さの考え方についてお話ししていきます。
金子: おふたりに合った建物のサイズ感を考えるといっても、実は土地も含めて検討しなければいけないのです。
祐樹(夫): なるほど、ここで土地が出てくるわけですね。
金子: そうなんです。当たり前ですが、家を建てるためには必ず土地が必要です。ただし、理想的なサイズの家が建てられるちょうど良い土地の広さを考えなければいけません。
家づくりは土地の広さも含めて考える
金子: 結論から言いますと、土地は狭過ぎても広過ぎてもダメなのです。
瑠璃子(妻): え、そうなんですか!?
金子: 良いリアクションですね。順を追ってご説明していきます。
まず狭い土地に家を建てるとなると、床面積を確保するために上へ階層を増やしていく必要があります。しかし、ある程度うまく設計したとしてもどうしても階段の昇り降りが発生することは避けられませんので、建主さんのご年齢によっては住みづらい家になることも考えられます。それに、平屋をご要望の場合は1階のみという構造上そもそも階層を増やせないので、ある程度広さに余裕のある土地を用意しなければ理想的な住みやすさを実現できません。
一方で、広ければ広いほど良いのかというとそれも考えものです。例えば、30坪の平屋を建築するために、100坪の土地を用意したとしましょう。その敷地のうち、7割が使わない土地ですから、よっぼど広々とした庭が欲しい方や畑を作って家庭菜園をしたいなどの利用目的が無ければ、使わない部分は無駄な土地になってしまいます。
この無駄な部分がどういうことをひき起こすかと言いますと、土地が広くなればなるほど取得費が高くなりますし、広さに応じて継続的に税金(固定資産税)がかかります。それを承知でも、整備する場合にはその分の外構工事費が必要です。そして日常的な掃除、庭の手入れ、草刈りなどの管理コストも考えなければいけません。そう考えると、広い土地は魅力的な反面、うまく活用できなければ長期的な負債になってしまうのです。
祐樹: うわぁ、負債になるのだけは絶対に避けたいですね。
金子: ですので、利用目的のはっきりしない広すぎる土地の取得はオススメしていません。
家づくりには狭すぎず広すぎずの「理想的な家に合うちょうど良い土地を用意する」というのがポイントです。
自分たちにとっての「ちょうど良い」を知る
金子: では「自分たちにとってのちょうど良い」とはどういう感覚なのか。それは現在おふたりが住んでいるおうちがひとつの基準となります。
家づくりをお考え中の方は、賃貸物件やご家族がお持ちの家で生活している方が大半だと思います。そこで得られる情報から、まずは今の居住空間での自分たちの現状を把握しましょう。
まず手始めに現在お住まいの居住空間の平米数を把握することをオススメしています。体感で得られる広さを数字で知っておくことで、後々のやり取りが円滑に進みます。もし家の平米数がわからなければ、各部屋ごとに何畳くらいの広さかを把握するのも良いでしょう。
そして最低限必要な部屋(リビング・寝室)や機能(キッチン・トイレ・浴室)を確認しながら、それぞれの部屋にどの程度の広さがほしいかを検討してください。いつも生活している家を俯瞰して見ることで、もっとトイレが広いほうが良いなとかキッチンにパントリーが欲しい、など普段気にしていないことにもだんだん気づいてきます。
それと合わせて現在の家の気に入っている点、不満がある点、これからの家づくりで実現したい理想などをおふたりで時間をかけて話し合うことが必要です。ここで深い議論ができればできるほど家づくりにはプラスに働くので、お互い遠慮せずに考えをすべて出し切ることが理想ですね。十分に話し合いの時間を取ることで自分たちの考えが整理され、だいたいの建物の規模感がぼんやり見えてきます。
瑠璃子: ほら、私がいつも言ってるじゃん。広いキッチンが良いとかもっと収納がいっぱい欲しいって!
祐樹: たしかに今の家には不満が多いよね…。
金子: その他にも手がかりとなるのが、他の家を見学することです。完成見学会があればまずは行ってみる、知り合いの家を見せてもらう、その他には金子に相談して過去に手掛けたお宅にアポを取って見学させてもらうなどですね。他の家を見学することで、そこに住む人のライフスタイルが色濃くわかり、部屋の大きさや間取りなど新たなヒントになることもよくありますので。住宅雑誌をパラパラめくるよりも、その場から感じ取れることのほうが何倍も多いですから。
そうして家のおおまかな規模感がわかってくると、必要な土地の広さも自ずとわかってくる、というわけです。
祐樹: 自分たちにとってちょうど良い家の規模感がわかれば土地が探せると。
自分たちに合った土地の探し方
金子: 大体の土地の広さの検討が付けば、次はどこのエリアで土地を探すのか、ということですね。
まず前提に生活圏として合っているかを考えましょう。
静かな場所が良い、利便性の良い場所が良いなど好みは人それぞれです。日常生活をする上で近隣にスーパーやコンビニの有無、学校をはじめとする公共施設への距離、仕事の通勤に困らない場所かどうかといった生活のしやすさはとても大事な判断材料ですよね。通勤・通学にどれくらいまでなら時間をかけても良いという話はこの時点でしておくと良いと思います。
祐樹: 僕の場合、自宅で仕事するので通勤時間はあまり考慮しなくても良いとして…。以前東京に住んでいたこともあって、ふたりとも利便性は重要視していますね。
金子: なるべく日常的なストレスのかからない環境を選ぶことだと思います。
そして次に個人的にオススメしているのが、土地を肌で感じることです。気になる土地が見つかったらぜひ実践していただきたいことは、実際にその土地へ行き現場を確認することに加えて、その土地の周りを歩いてみてください。車で周りを通り過ぎるだけではダメですよ、自分の足で歩いて観察するんです。
その土地の空気や匂い、耳に入ってくる音、そして土地の日当たりや景観のすべてが判断材料になります。土地情報や写真を見るだけで満足してはいけません。現場にこそ生きた情報があるからです。
祐樹: たしかに土地情報には載っていないことって見落としがちですね。
金子: そうなんです。それに平日仕事の方は週末に土地を探される方も多いと思うのですが、週末は静かだけど平日は近くの会社で作業音が鳴り響いて意外と平日のほうがうるさいなんてことも実際によくあります。ですので、焦らずゆっくり見てみるというのも土地選びのポイントです。土地を手に入れることは早い者勝ちなので、みなさん早くしないと誰かに取られてしまうと考えがちです。でも、新潟のような地方であれば意外と急がなくても買えることが多いですし、不動産屋と交渉すれば他の人に買われないようにキープできる場合もありますから、何度も足を運んで土地とその周辺をじっくり見ていただきたいですね。
そして最終的には直感で選ぶことも大事だと思います。結局直感かよ!と思うかもしれませんが、土地選びで一番大事なのはその人がその土地を好きかどうかということに尽きます。家を建てることは、つまりその土地で長く住むということなので、気に入った場所に建てた気に入った家で日々幸せを感じて生活する。これが今後の人生を豊かにするという最善の選択ではないでしょうか。
瑠璃子: その通りですよね。いくら土地の条件が良くて素敵な家が手に入っても、自分が好きではない場所に我慢しながら住むのは苦しいかもしれないです。
土地を決める前でも相談に乗ります
金子: もちろん、土地が決まっていなくても、その前に相談していただければ土地探しからお手伝いさせていただきます。むしろ土地探しを一緒に行うほうがメリットが多いのです。
というのも、検討敷地を購入する前に先駆けてプラン検討を進められることが一番のメリットとして挙げられます。見つけた土地で希望の家が実現可能かの判断ができますし、仮にその土地に立派な既存樹木があれば、敢えてそれを活かしたプランに調整するなどその土地に合わせて柔軟に設計提案ができます。逆に条件が悪ければ「この土地はやめたほうが良いです」とお伝えもしています。
祐樹: それなら、なおさらお願いするべきですね。
金子: 初めての家づくりでは土地探しはやはり簡単なものではないので、一緒に土地を探すほうが建て主さんにとって安心だと思います。土地がまだ決まっていなくてもお気軽に相談してください。とはいえ、既に土地をお持ちの方であっても、その土地を効果的に利用できるよう最善を尽くしますのでご安心ください。
金子: そういえば先ほど少しお話ししましたが、平屋や2階建てなど構造については今の時点でご希望ありますか?
祐樹: それがまだ迷っていて、どちらか決めきれていないんです。
金子: わかりました。では次は家の構造についてお話ししましょうか。
この記事のまとめ
- 理想的な家に合った「ちょうど良い土地」を探す。
- ちょうど良いを知る第1歩は、現在の住まいから広さを把握すること。
- 他の家の事例をたくさん見て、家づくりのアイデアの引き出しを増やす。
- 生活圏として合っているか、実際に検討敷地やその周辺を歩いてみて、最後は自分の直感で選ぶ。
- 土地探しから設計相談をすることで、柔軟な提案が受けられる。
(連載5回目に続きます)